はじめに
函館旅の締めくくりに選んだのは、やっぱり定番の「函館山」。
夜景で有名なスポットだけど、今回は昼間の景色を楽しむことにしました。
春の澄んだ空気の中、ロープウェイで山頂へ。
歴史と地形が交差するこの場所で、函館という街の奥行きを感じる時間になりました。
函館山の概要とアクセスの印象
函館山は標高334m。市街地のすぐそばにあるとは思えないほど、展望台からの眺めは壮大です。
ロープウェイでアクセスするのが一般的ですが、驚いたのはその山麓駅の立地。
普通に住宅街の中にあって、「え、ここから登るの?」とちょっと意外な印象。
観光地というより、地元の生活圏に溶け込んでいる感じがして、なんだか親しみが湧きました。
展望台から函館の街並みを一望

山頂に着くと、まず目に飛び込んできたのが函館の街並み。
この写真は、夜景で有名なアングルを昼間に撮ったもの。
街の中心部がくっきりと見渡せて、遠くの山の頂上付近にはまだ雪が残っているのが印象的でした。
春とはいえ、北国の季節の移ろいを感じる瞬間。
五稜郭の位置も遠くに確認できて、「あそこからここまで来たんだな」と旅の流れを振り返ることができました。
函館港方向の眺望と歴史の実感

次に目を向けたのは函館港方面。
この写真は、港を見下ろしたもの。
トンネルが開通する前は、青森との間を連絡船が行き来していたと知って、港の広がりが歴史の舞台に見えてきました。
今はフェリーや観光船が行き交う穏やかな海だけど、かつての交通の要所だったことを思うと、風景の見え方が変わります。
津軽海峡の向こうに本州を望む

展望台からさらに目を凝らすと、津軽海峡の向こうに本州がうっすらと見えました。
この写真は、その方向を撮ったもの。
「あの向こうが青森か…」と想像すると、地理的なつながりがぐっとリアルに感じられます。
海を挟んで向こう側にある別の土地が、こうして視界に入るって、なんだか不思議な感覚ですよね。
魚住漁港方面と谷地頭の記憶

最後に見下ろしたのは、ふもとの魚住漁港方面。
この写真は、そのエリアを撮ったもの。
ブラタモリで見た谷地頭がこのあたりにあると知って、「あ、ここか!」と記憶がリンク。
地形の特徴や街の成り立ちを思い出しながら、次は実際に歩いてみようと決めました。
こういう“地形と記憶のつながり”って、旅の醍醐味のひとつだと思います。
まとめ・次回予告
函館山からの眺望は、ただの絶景ではなく、歴史や地理のつながりを感じられる場所でした。
ロープウェイでのアクセスも含めて、旅の締めくくりにふさわしいスポット。
次回は、函館の市街地を歩いた街歩き編をお届けします。
地形と歴史を足で感じる、函館旅のラストスパートです。
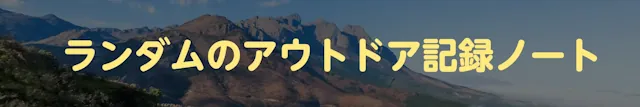




コメント