
はじめに|谷川岳の奥へ、静かな道を歩く
谷川岳ロープウェイで天神峠を訪れた翌日、旅の締めくくりとして一ノ倉沢出合まで歩いてみることにした。10年前に訪れたときは河原まで足を伸ばしたが、今回は出合までの道のりをじっくり味わうことにした。
秋の谷川岳は、紅葉にはまだ少し早く、緑が濃い。空気は澄んでいて、歩くたびに葉のこすれる音や、遠くの沢の水音が耳に心地よく響く。静かな山道を歩く時間は、街では味わえない贅沢だ。
谷川岳山岳資料館からスタート

スタート地点は「谷川岳山岳資料館」。この写真はその外観。木造の落ち着いた建物で、登山者や観光客が立ち寄る拠点になっている。
車で来られるのはここまで。この先は車両通行止めだが、自転車は通行可能。ガイド付きの乗り合い電気バスもあるらしく、歩くのが難しい人にはありがたい選択肢だ。
資料館の前で深呼吸をして、いざ出発。舗装された道をゆっくりと進んでいく。
国道291号と清水峠道の歴史
歩いている道は国道291号。今では新潟側には抜けられないが、明治18年に開通した清水峠道の一部だという。かつては馬車も通った道らしく、勾配が緩やかで歩きやすい。

途中、石垣が現れる。この写真はその石垣。解説看板には「明治時代の石垣がところどころに見られる」と書かれていた。苔むした石の並びに、時代の重みを感じる。
道の両側には木々が立ち並び、風が吹くと葉がさざめく。歴史の道を歩いているという実感が、足取りを軽くしてくれる。

登山指導センターと熊の張り紙

しばらく進むと「谷川岳登山指導センター」が見えてくる。建物の前には「昨日、天神尾根にて親子熊の目撃情報あり。注意してください。」という張り紙が貼られていた。この写真はその張り紙。
最近は全国的に熊の出没が増えている。山に入る以上、自然との距離感を意識することは大切だ。少し緊張しながらも、周囲の音に耳を澄ませて歩き続ける。
一ノ倉沢までの道のり

資料館から一ノ倉沢出合までは徒歩で約50分。道は緩やかで、歩きやすい。途中、石垣や沢の音に癒されながら、ゆっくりと進む。
人もまばらで、時折すれ違う登山者と挨拶を交わす。こういう何気ない交流も、山歩きの楽しみのひとつだ。
一ノ倉沢出合に到着

ついに一ノ倉沢出合に到着。この写真はその絶景。目の前に広がる雄大な岸壁は、何度見ても圧倒される。
頂上付近には雲がかかっていて、残念ながら全貌は見えなかったが、中腹には白く輝く万年雪が残っていた。今年の暑い夏を乗り越えた雪が、静かにそこにある。

無料の望遠鏡が設置されていたので、覗いてみることに。スマホのカメラをレンズに合わせてみたら、意外と綺麗に撮影できた。この写真はその万年雪のアップ。望遠鏡越しの風景が、手元に残るのは嬉しい発見だった。
帰路と土合駅の構造

今回は河原までは行かず、出合で折り返すことにした。帰りは土合駅から普通列車で水上・東京方面へ。
土合駅の水上・東京方面ホームは地上にある。下り線の地下ホームとは対照的で、駅の構造のユニークさが際立つ。この写真は地上ホームの様子。山の空気に包まれた静かなホームが、旅の終わりを優しく告げてくれた。

まとめ|歩いてこそ見える谷川岳の表情
一ノ倉沢出合までの道は、自然と歴史が交差する静かな旅路だった。歩くことで見えてくる風景や、石垣の名残、熊の張り紙に感じる緊張感。どれも谷川岳の“今”を教えてくれる。
次は都内から自転車で自走して一ノ倉沢を訪れるのも面白そうだ。季節を変えて、またこの道を歩いてみたい。今回の旅はここまで。読んでくださってありがとうございました。
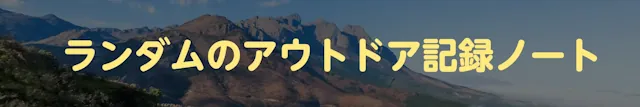




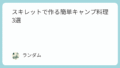

コメント